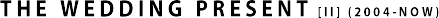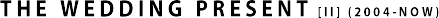Scopitones
TONE CD 020
 | TAKE FOUNTAIN
FORMAT: STUDIO ALBUM
RELEASE DATE (U.K.): 14th February, 2005
LABEL / CATALOGUE No:
Scopitones (U.K. ) CD / TONE CD 020
Scopitones (U.K. ) 2LP / TONE 020 ; released on 18th April, 2015 1,000copies limited
Manifesto (U.S.&Canada) / MFO-43901 ; released on 15th February, 2005
Stickman Records (Germany) / Psychobabble 047 ; released on 14th February, 2005
Talitres (France) / Tal-019 ; released on 15th February, 2005
Houston Party Records (Spain)/ released on 1st March, 2005
TRACK LISTING:
(Original U.K. Scopitones' edition)- On Ramp
- Interstate 5 [Extended Version]
- Always The Quiet One
- I'm From Further North Than You
- Mars Sparkles Down On Me
- Ringway To SeaTac
- Don't Touch That Dial [Pacific Northwest Version]
- It's For You
- Larry's
- Queen Anne
- Perfect Blue
PERSONNEL:
David Gedge : Singing, Guitar and Percusion
Simon Cleave : Guitar
Terry de Castro : Bass and Backing Vocals
Kari Paavola : Drums and Percussion
with the assistance of : Steve Fisk (Vibraphone, Glockenspiel, Mellotron, Organ and Piano), Jen Kozel (Violin), Stephen Cresswell (Viola), Lori Goldston (Cello), Don Crevie (Fench Horn), Jeff McGrath (Trumpet)
All the songs were written by David Gedge & Simon Cleave. Produced engeneered and mixed by Steve Fisk. Additional production by David Gedge & Simon Cleave. Orchestral Arrangements by David Gedge. Dedicated to the memory of John Peel. |